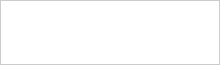毎日毎日暑い日が続いております。
皆さまにおかれましては熱中症等ならないよう水分補給や適度なエアコンの使用、
暑い日は不要不急の外出を避けるなど対策をお願い致します。
先日は信者さんのお墓での法要をさせて頂きましたが汗が止まりませんでした。
礼拝所も取っても取っても草が生えてしまいます。
暑いのでなかなか草取りをする時間を考えながら、実施しています。
さて、法要法事はなぜ行うのでしょうか?
法事・法要は、故人を偲び、冥福を祈る仏教の儀式です。単なる形式ではなく、故人、遺族、そして仏教の教えにとって深い意味を持つ重要な行事です。
法事・法要の主な意味
1. 故人の追善供養のため
仏教では、故人がより良い世界(浄土)へ旅立てるよう、生きている人が善行を積んで故人の冥福を祈ることが大切だと考えます。この行為を追善供養(ついぜんくよう)といい、法事・法要は、この追善供養の最も代表的な行事です。故人様のご遺族や関係者の皆様が集まり、僧侶に読経を依頼することで、故人様の霊が安らかになるよう供養します。この供養は、故人様だけでなく、追善供養をした方々自身の徳も積むことになります。
2. 故人との繋がりを再確認するため
法事・法要は、故人様を想い、その存在を心に刻む大切な機会です。特に、七回忌や十三回忌といった節目で行われる法事は、故人様が亡くなってから年月が経ち、記憶が薄れつつある中で、その存在を改めて思い出し、故人様との思い出を語り合う場となります。これにより、ご遺族は故人様との精神的な繋がりを再確認し、心の安らぎを得ることができます。
3. 遺族や親族の交流の場として
法事・法要には、故人様のご親族や関係者の皆様が集まります。遠方に住んでいて普段なかなか会えないご親族が一堂に会する貴重な機会となります。法事後の会食(お斎)などを通して、互いの近況を語り合い、親族間の絆を深めることができます。これは、故人様が遺してくれた大切な縁であり、その繋がりを維持する役割も果たしています。
4. 仏教の教えを学ぶ機会として
法事・法要では、僧侶が読経の後に法話をすることが一般的です。法話は、仏教の教えを分かりやすく説くもので、参列者は、故人様を通して、人生のはかなさ(無常、つねにおなじものはない)や、生かされていることへの感謝など、仏教の精神に触れることができます。これにより、自身の生き方を見つめ直すきっかけにもなります。
主な法事・法要の時期
法事・法要は、故人が亡くなった日から数えて特定の節目で行われます。
- 初七日(しょなのか):亡くなった日から7日目
- (七七日)四十九日(しじゅうくにち):亡くなった日から49日目。この日で故人様の魂の行き先が決まるとされるため、最も重要な法要です。
- 百箇日(ひゃっかにち):亡くなった日から100日目
- 一周忌(いっしゅうき):亡くなった日から満1年目
- 三回忌(さんかいき):亡くなった日から満2年目(3年目の同じ日に行う)
- 七回忌(ななかいき):亡くなった日から満6年目(7年目の同じ日に行う)
- 十三回忌(じゅうさんかいき):亡くなった日から満12年目(13年目の同じ日に行う)
以降も、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌など、故人を供養する節目が続きます。
これらの法事・法要は、単に義務として行うものではなく、故人様への感謝を伝え、ご遺族の心の整理を促し、ご親族の絆を深めるための、意義深い儀式なのです。